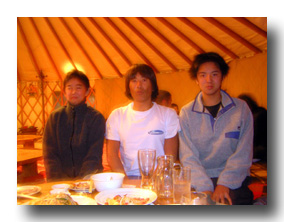
|
2004年1月○日
■ ■ ■ ■ ■
毎年、この時期になるとパウダースノウを求めて、ニセコ通いの日々が続くが、今年は家族全員揃ってのニセコ参りとなった。
いつもニセコに一緒に通っている、雑誌「ターザン編集部」の内坂氏も我々家族に同行し、我が息子を秘密のポイントに案内してくれ、木立の間を駆け抜け、誰もいない山を滑り降り、森の中を転げ周り、存分にバックカントリーの世界を堪能させてくれた。(「フォトギャラリー」のコーナーを参照)
そして夜はお馴染みの「玄天カフェ」で夕食。
ここはモンゴルの「パオ」を使ったレストランで、その異次元的な空間といい、エスニックな味わいといい、我々がニセコでもっとも気に入っているお店だ。
デザートも充実しているし、子どもたちにも大好評だった。
|